

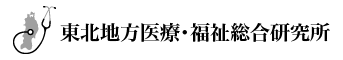
医学者としてのヒポクラテスの偉大さは、医学・医術(元来、それらは、テクネー〈techne, ars, art〉という言葉に共に含まれていた)から、呪術的要素と不毛な思弁とを払拭して、それを経験的な科学としてはじめて組織しようとしたことにあった。
彼は、病因を、血液、粘液、胆汁、黒胆汁という4つの体液*の「混和(crasis クラーシス)の失調(dyscrasia デュスクラジア)」に求めた。
心臓にその座をもついわゆる内在熱(innate heat)による「調理」(coction)によって、その調和が保たれるというのである。
こうして、彼は古典ギリシアの生んだもっとも卓越した自然科学者の一人であったと言うことができる。
しかも彼は、科学者として当然と言えば当然のことながら、その科学の現況について冷静で正確な認識をもっていた。
つまり、その当時の限界を弁えていたのである。
医師とは人の身体に発する「悩み」に最善の「テクニカルな」助力を提供する義務を負った職業(プロフェッション)を与えられた人の意味である。その職業はヒポクラテスにおいて比類まれな高みにおいて体現された。
有名な「誓い」(「ヒポクラテスの誓い」Hippcratic Oath)については、彼とは別に扱わなければならない。近年の有力な研究によれば*、ヒポクラテスないしコス派の著作でなく、おそらくはピュタゴラス教団の医師の手になったものと言われる。医師セクトへの一種の入門誓約書であるこの短文が、あたかも医師一般の正統的な信仰箇条のように信奉されるようになったのは、中世キリスト教世界でのできごとであった。
そこで述べられている職業倫理の核心は、後半の冒頭に記されている、(1)「私は病者のために(for the benefit of the sick)自分の技術の最善を尽くす(according to my ability)と、(2)「何はともあれけっして危害や不正は加えない」(primun non nocere)との二点に存したと観て間違いない。
また、同じく『集典』中に含まれるおそらくは若い医師たちに対する教育的の意図に基づいて著わされたと推測されるいくつかの作品は、その倫理的な高みと医業の性格に関する意識の鋭さのゆえにきわめて印象的だが、永くヒポクラテスに帰せられていたそれらの文書の成立は実はよほど遅れて、そこにはエピクロス派やストア派の倫理思想の強い影響も見えると言われる。
「医聖ヒポクラテス」というとらえ方も、少なくとも学問的には慎重に受けとることが必要である。しかし、それらの事実を総合して見ると、ヒポクラテスというたしかに実在した人格、学識ともに卓抜な医師の名によって象徴される一群のきわめてすぐれた医師たちの集団の活動があったことを認めざるをえない。
病気は「人の悩み」の非常に重要な側面である。おのずからそこに呪術や、いろいろな意味での宗教の出番がある。
ギリシアの学者たちが、その人を「自然」の中ではじめて眺めたとき、医学は科学的基盤を持とうとする方向へ大きく転回した。しかし現実に悩みの中にある病人を前にして、自然哲学的な「本性」(nature)を論じても空虚な話である。
ヒポクラテスの偉大さは、古典ギリシアが新たに発見した自然(科学的に把握しうる存在としての)の中で、病気の経験科学へのアプロ-チを企てたこと(体液病理学主義的傾向を持つ)、同時にまた、そのアプローチが単なる自然現象にとどまらず、ほかでもない人間の病気であることを見誤らずに、科学者である医者の、患者対医者という人間関係における正しい位置を見さだめ、それに従って考え、行動した点にあった。
ヒポクラテスにも限界はあった。盛期ヘレニズムの科学的雰囲気の中で、アレクサンドリアの医学者(エラシストラトスが中心)たちが、多分に独断的であったヒポクラテスの医学を、解剖学、生理学をかたく踏まえて病気の科学的な理解を志す軌道に乗せた。それは医学のその後の歩みに決定的な方向づけを与えるものであった。しかし、その道はにわかに報いられぬきわめて困難なものであった。実際に科学的医学が実際に有効性を発揮するのは、19世紀になってからであった。
ヒポクラテスと同じく、感覚を武器とする経験的なアプロ-チにたよるガレノスの医学は、解剖学、生理学の医学的な意義を見落とさない。
初期アレクサンドリア医学者たちの豊かな遺産を踏まえた。
生体のはたらきがその構造の知識を欠いては理解できないこと、そして病気を諸器官のはたらきの障害として考察する医学者ガレノスにとって解剖学の意味ははなはだ重かった。
その点で彼は疑いもなく医学のヒポクラテス段階から大きく踏み出している。
彼自身が、優れた解剖学者であった。
彼は、動物の解剖しかできなかったが、傑作『解剖法について』を読めば、以下に優れた解剖学者であったかが分かる。
しかも彼は、マクロの解剖学に通暁したばかりでなく、皮膚、軟骨、骨、脂肪その他の(単純)組織と、それらによって構成される諸器官の構造に関する正鵠をえた知識までもっていた。
それは、医学史において、現代組織学の開拓者であるビシャの業績を先取りするものであったと評価されている。
ガレノスは、生物現象を、アリストテレス(前384〜322)的な動き(kinēsis, motion)ないし変化においてとらえ、動きの基本的なものとして、生成、生長、および栄養(同化)に着目する。現代の眼から見ても、そこには生物学の基本的な範疇に対する驚くほど深い洞察があった。
それらのはたらきを「能力」(dynamis, facultas, faculty)とよぶ。この生理学と解剖学とを結びつけるところにガレノスの生物学の中心問題があったとみてよい。
生物現象における質の変化の相を重くみるガレノスは、原子論に立つ機械論的な生物理解をきびしく斥け、それは生物の精妙な諸能力とそれを支える原理への理解の道でないとする。
ガレノスの理解はおよそ次のようであった。
食物も飲料も四元素(火、水、土、空気)より構成されるが、消化によって例の四つの体液(血液、粘液、胆汁および黒胆汁)に変わり、組織を養う。脈管中を流れるのは、その混合物だが、しかしその主役は血液である。
栄養物を運ぶ同じ血液が、あるいは骨、筋肉、腎臓等々といったさまざまの組織や器官の材料となる(現代風に言いかえれば特異化する)、という不思議な事実を炯眼にも見のがさなかったガレノスは、その過程を血液の供給、停留、特異的な牽引、といった一連の「能力」(前述)に分けて説明する。
その「能力」の概念はこうした生化学的な諸問題のみならず、進んで器官生理学のさまざまな現象の説明にも、型のようにもち出される、ガレノス生物学のキー・ワードであった。組織が栄養を特異化する「能力」をもち、子宮が胎児を保存する「能力」と時期が来てそれを娩出する「能力」をもつというのである。
もちろん、ガレノスの「能力」は、現代では、証明なしの万能概念だと批判されることが多い。その批判はまったく正しい。
しかし、それらの諸現象のメカニズムが、科学的な形で表現されるようになったのは、19世紀の後半以後であり、あるものは20世紀になってからであることを想起すれば、安易な批判は意味がない。
むしろ、1900年も前に、ガレノスが、常識的には食物の消化と栄養というほどの現象の中から、代謝の本質に触れる諸問題を抽きだし、大枠を説明したことに見られるように、正確に観察された生物現象を諸「能力」といういわば枠組の形で科学的な解析に導こうとした生物学者ガレノスの卓抜した能力を、高く評価すべきであろう。
ガレノスは、原理的には四体液説を堅持した上で、正確な解剖学的知識を踏まえて、病気を諸器官の機能の障害と観る。目的論者であるガレノスにとっては、諸器官すなわち部分は全体に仕えるためにあるので、器官にとらわれて全身を見る眼が曇るということはない。