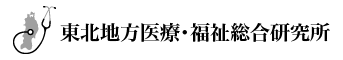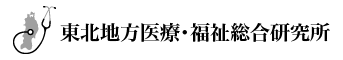
【医学部新設に対する資料】
【医学部新設賛成者―進め方への意見】
末尾の(保)は保健師、その他は医師
〈どんな医学部を作るか〉
- 東北の医学部を卒業したら東北の病院に就職する等のシステムをつくると共に公衆衛生の学部学科を設けて頂くと災害時にも強い医師に成長できることを期待する(保)。
- 高齢社会に対応した老人専門分野にも力を入れて頂きたい。
- 予防医学、栄養学などもしっかりやって貰いたい。
現医師にも公開授業や何かの資格がとれるようにしてもらいたい。
- 癒しの心がわかる医師の養成に心がけてほしい。そのためには入学者選抜の段階から自然科学だけに偏らない方法を工夫してほしい。
- 防災教育、予防医学、地域と密着した地域医療、西洋医学と東洋医学との融合などの教育内容について総合的な医学教育内容について検討委員会を設置して教育方針を決めること。
- 超高齢化社会にむけて在宅医療推進。
- 総合診療医育成。地域出身者優先。
- プライマリケア重視の教育を行う。
- 地域で活動できる臨床医を育てる事を第一の目標にしてほしい。
- 救急医療に特化してほしい。
- 地域医療、過疎地医療を真剣に考えとりくんでくれる医師を養成してほしい。医師数が多いことはよいことです(保)。
- 被災地、東北地方の医師不足解消のための養成をしてほしい。
- 被災地や東北地方発展を引き起こす医学部が生まれることを期待する。
- 地域医療に貢献できる人材育成を。現大学のコントロール下にある大学ではなく競合できる大学として自立した運営を。
質の低下を防ぐこと。
- 卒業生が僻地に勤務することを義務づけ総合診療科を充実させるような工夫。
- “教育>診療>研究”を基本理念とする。
- 既設の医学部ではない新しい校風を。臨床医養成を一番に。
- 医療福祉全体を向上させねば医学部単独での新設はありえない。
- 最初は定員30~50くらいでいかがでしょうか。
- 東北大学との住み分け、コンセプトの違いが必要。
- 東北地方の中心県として公的に医師養成大学を創設するのはむしろ当然の責任。
東北大学医学部と違った意味の医科大学設置を望む。
- 東北地方の医師過疎地域に資する考えに的を絞るならば、広く地域医療に関心を持つ若者に利する医科大学にすべきであり、公立が望ましい。
一定期間の僻地医療を必修とし2年の前期研後ローテートする。
- 東北諸県が共同して自治医大東北版の検討。
- 自治医大や産業医大などと同形式でも。
- 質の低下を防ぐこと。
〈条件〉
- 学生の教育に関する費用は全額公費負担とすべき。
経済的に貧困な人たちも医学部に入学できない状況をなくすために。
- 地域に残る医師を育てるには県立など公営にし奨学金制度を設ける。
研究はせずに現場の視点、心ある医師を育てる医学部にする。
- 国民の命を預かる養成は、公的機関で行ってほしい。
教師も身分を安定した条件であることこそ、住民の願い。
くらし、そこから発生する病を抱えての暮らしが見える医師の養成が出来ると思うからです(保)。
- 経済的制約なく志ある若者が勉学できる条件を実現すること。
- 目的や理念からは国公立にする。経営的に安定する。
- 国の新設医大の条件①②④は公立医学部であるべき。それが前提で賛成。
- 国の方針③を期待します。
- 経済的に問題が起こらないように充分検討下さい。
- 2/2付河北新報の持論時論を拝見するまでは、私立と思っていましたが県立に代わりました(保)。
- 男子校にしてほしい。
- 地域枠を50%以上にしてほしい。
- 当落線上の受験者に対し可能な限り地元出身の受験者を選んでほしい(関西や九州の人を選んでも、いずれ地元に帰ると思われる。
- 自治医大のように卒後10年位は被災地で診療に従事することを確約させることを条件に学生を募集すること。
特別な目的での新設であることを学生に周知させること。
- 地方で働く医師となる担保の確立。
- 東北地方に定着することを条件にする。
- 卒業生が東北地方の病院に就職することを義務付ける。
- 東北に残るために自治体の財政措置で残るようにする。
- 東北の医師不足は明らかに存在する厳然たる事実である。
被災地や東北の医師不足解消に役立つような方策を常に考えてほしい。
- 地方勤務の医師が増えるシステムを何とか構築してほしい。
- 5年後に定数や方針の検討を繰り返し東北地方の医師不足に対応していく。
- 県立なら、卒業後5年間は東北6県の僻地に勤務の義務などの条件を付ける。
- 私立でも、県で助成し、どの地域でも医療を行う医師養成システム、体制が必要。
- 校舎を沿岸部に。
- 人数を多めに、県立で安く。
- 現大学のコントロール下にある大学ではなく、競合できる大学として自立した運営を。
- 臨床第一主義に医学校を。既設医学部の定員を元に戻すべき。
〈役割期待〉
- 公的、私的関係なく医師、看護師を送り込む母体となってほしい。
現状は官尊民卑がひどすぎる(特に宮城県)。
- できるだけ早く。設立母体に拘らない
〈進め方〉
- 医師確保に苦労している地方の病院長などの意見を取り入れて進めてほしい。
- 国がイニシアチブをとって教育スタッフも地方中心でなく全国から集めるようにしてほしい。
- どの程度の規模の医大になるか、現在の進行度について、その都度ヒアリングしてほしい。
- 知事が決定権を持っていて決定条件を開示しないのは問題だ。裏のかけ引きで既に決定されているような報道であり不明朗な何か取引があるかの様な感じがする。
決定経過について定期的に県民に開示してほしい。県民が意見を言える場は全くないのか。
- 国、県、県議会 すべてが納得する条件で。
- ①新設を希望している方の話し合い(一緒にできないか)②委員会を作り相談③経営のことを考えて④一緒にできないなら国に決定をゆだねる。
- 現在、新設へ手上げしているのが2団体あるが協力して話し合いするのが良いと思います。
- 仙台厚生病院を母体に作るべき。政治団体がbackにある病院は関与すべきでない。
- 病院+大学:県の方針に従い2~3の企業集団で協議する。
- 厚生病院、薬科大どちらでもよいと考える。予定通り進むことを期待。
- 目的達成のため関係者は100年の大計を考慮し、小異を捨て大同につくべきと考える。
- 早く進めてほしい。
〈その他〉
- 現在、東北薬科大学、福祉大、学院大が新設をめざし、受け入れ自治体として栗原市が決まり、石巻市も基礎医学部の誘致に乗り出していますが、全体的な方向が見えません。
医学教育がそう簡単にできるとも思いませんし。この流れに危惧を感じます。
医学教育と地域医療の実態(要求)をどうリンクさせるか、今後の課題と思います。
- 震災復興、東北地方の医師人材不足確保の目的はよい。加えて、地域活性(過疎、高齢者対策)、キャンパスの場所確保、交通の便などの点で、栗原は理に適っている。
是非実現に向けて労を取ってほしい。
- 医師過剰が心配されますが栗原市の発展のためにはやむをえないのでは。
- 仙台市内に作ってください。栗原では遠すぎて、何かと不便です。
- 私立では国の方針を実現しづらい。
- 情報公開は国公立では強く求めることが出来ますが、私学だとどこまで可能か。
教授選など人事に関心があります。臨床のできる方を選ぶべきです。
- 県税は、他に優先的に使う事業があるので私立で。
- 設立母体に拘らない。
- バランスのとれた医師分布には中核病院・基幹病院の設置・充実(ハード、ソフト両面で)が絶対条件。
現状のままでは医学部新設し医師数を増やしても医師集中、医療格差が進むだけ。新設するなら受け皿としての各地の病院整備を。
- 厚労省の医療政策を変えなければ、田舎に医師も看護師も来ない。
病院経営も大変。地域による基準看護とか、医師配置基準を変えないと、地方の医療は崩壊するし、東北や北海道等僻地に医師も看護師もいくら養成しても止まらなくなると予想される。
- ①医師配置の地域間格差をなくし、どこに居住しても十分な医療が受けられる社会の構築のため ②都市部の勤務医も過重な労働、長時間労働は当たり前のような状況にある。医師配置を増やし労働条件を改善する必要ある。
- 東北地方には必要。
- 仙台周辺地域にとどまる医師養成の医学部が必要。
- 農学部跡地の利用を。
Copyright ©東北地方医療・福祉総合研究所 All rights reserved.